
トップページ > カテゴリー「八代」 での検索結果(1722件ヒット)


まもなくスタートします・・・

いかだ組み講習会=八代市。小学校の先生が、「筏流し」を児童に教えようと、まず筏の組み方から始めた。木材を葛やふじ葛で結束した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和61年09月05日
撮影:1986年9月
いかだ組み講習会=八代市。小学校の先生が、「筏流し」を児童に教える

弓道の練習。八代弓道連盟・夏期講習が夕葉橋下の球磨川右岸で、昼の人通りがない時間に弓を引いて練習に励んだ=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和59年07月11日
撮影:1984年7月
弓道の練習=八代市

日奈久のちくわ焼き=八代市。温泉神社の春まつりのアトラクションに日奈久名物竹輪つくりが行われ、各人が3本ずつ炭火で焼き、おいしい香りが境内にただよった (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和58年04月03日
撮影:1983年4月
日奈久のちくわ焼き=八代市。温泉神社の春まつりのアトラクションに日奈久名
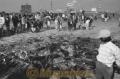
どんどや=八代市。正月が終わり、毎年7日には校区でどんど焼きが行われた。直径4~5メートル、高さ6メートル位の竹組に正月の飾り物を焼き、その火で餅を焼いて食べた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和58年01月07日
撮影:1983年1月
どんどや=八代市。正月が終わり、毎年7日には校区でどんど焼きが行われた。

日奈久温泉神社の神幸行列=八代市。温泉神社の神幸行列に子供たちの魚みこしも加わり、元気に町内を練り歩いた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和57年10月15日
撮影:1982年10月
日奈久温泉神社の神幸行列=八代市。温泉神社の神幸行列に子供たちの魚みこし

大きなちくわ焼き=八代市。日奈久温泉の「丑(うし)の湯まつり」で大きな「ジャンボ竹輪」が焼かれた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和55年07月26日
撮影:1980年7月
大きなちくわ焼き=八代市。日奈久温泉の「丑(うし)の湯まつり」

工都を見続けた旧日本セメントの煙突=八代市。明治23年操業で、戦争、終戦、復興、高度成長、オイルショック…と時代を生きた煙突は、海からも目印として役だった (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和53年09月01日
撮影:1978年9月
工都を見続けた旧日本セメントの煙突=八代市。明治23年操業で、戦争、終戦

日奈久駅と馬車=八代市。日奈久駅前を出発する馬車 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和52年07月25日
撮影:1977年7月
日奈久駅と馬車=八代市。日奈久駅前を出発する馬車 (麦島勝氏撮影)

ハゼの実取り=八代市。球磨川右岸の堤は「ハゼ」並木で秋は紅葉が川辺に映え、すばらしい景観で冬になるとローソクをつくる「ハゼの実」が採取された (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和52年01月20日
撮影:1977年1月
ハゼの実取り=八代市。球磨川右岸の堤は「ハゼ」並木で秋は紅葉が川辺に映え

講堂横で保護者と一緒に記念撮影=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和51年04月01日
撮影:1976年4月
一年生の入学記念写真=八代市

日奈久駅=八代市。九州を代表する温泉地として、駅は毎日温泉客で賑わう。人気の客馬車も見える。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和50年05月15日
撮影:1975年5月
日奈久駅=八代市。九州を代表する温泉地として、駅は毎日温泉客で賑わう

田植えの前の代かき=坂本村 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和49年05月24日
撮影:1974年5月
田植えの前の代かき=坂本村 (麦島勝氏撮影)

鮎干し=八代市萩原町。落ちアユは腹から卵粒を取り出し「うるか」に加工され、串に刺され焼かれたり干されたりした。球磨川の晩秋の風物詩 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和48年11月08日
撮影:1973年11月
鮎干し=八代市萩原町。落ちアユは腹から卵粒を取り出し「うるか」に加工され

日奈久温泉を走る客馬車 =八代市。国道3号を車に混じって客馬車がゆっくり進む。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和48年10月15日
撮影:1973年10月
日奈久温泉を走る客馬車 =八代市。国道3号を車に混じって客馬車がゆっくり

客馬車=八代市。日奈久駅からお客さんを乗せて国道3号を軽快に各旅館をめざし進んだ (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和48年09月02日
撮影:1973年9月
客馬車=八代市。日奈久駅からお客さんを乗せて国道3号を軽快に各旅館をめざ
