
トップページ > カテゴリー「八代」 での検索結果(1722件ヒット)


まもなくスタートします・・・

日奈久の石桟敷=八代市。日奈久のお祭りやいろんなイベントでは、温泉神社境内に設けられた石桟敷が野外の会場になって旅館が借り切ってお客さんをもてなした (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年03月15日
撮影:1953年3月
日奈久の石桟敷=八代市。日奈久のお祭りやいろんなイベントでは、温泉神社境
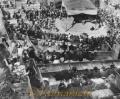
日奈久の石桟敷=八代市。日奈久温泉神社境内には、参道の斜面に階段状に石の桟敷席が設けられ、相撲や歌や踊りなど、いろんなイベントに利用されている。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年03月15日
撮影:1953年3月
日奈久の石桟敷=八代市。日奈久温泉神社境内には、参道の斜面に階段状に石の

寒行=八代市。お寺の住職を先頭に団扇太鼓を打ち鳴らし「南無妙ホーレンゲキョー」と声を出し、老若男女の信者が町をめぐる大寒行事 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年01月20日
撮影:1953年1月
寒行=八代市。お寺の住職を先頭に団扇太鼓を打ち鳴らし「南無妙ホーレンゲキ

餅からい=八代市植柳町。誕生日前に歩き出した子供は、親を離れて他国へ行かないようにお供え「餅」を背中に結び付けて歩かせた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年01月20日
撮影:1953年1月
餅からい=八代市植柳町。誕生日前に歩き出した子供は、親を離れて他国へ行か

歳末大売出しの景品引き換え=八代市。八代市通町の旅館酒井屋での歳末大売り出し景品抽選引換の行列は隣町の出町まで続き、バスの通行にも支障が生じていた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年01月02日
撮影:1953年1月
歳末大売出しの景品引き換え=八代市。八代市通町の旅館酒井屋での歳末大売り

年始まわり=八代市。みなと祭りや神社の秋祭りには、カヌー競漕や相撲大会や神行行列があり、市内のいろんな企業が参加する仮装行列で盛り上がる。日常の繁栄と平和を祈る市民の感謝のあらわれである (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年01月01日
撮影:1953年1月
年始まわり=八代市

年始まわり=八代市。家庭でおとそや雑煮で新年を祝い、上司や親類の家に年始まわりに行く。日の丸の旗をつけたダットサンや紋付きはかまのお父さんに手を引かれた坊やの姿も見える。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年01月01日
撮影:1953年1月
年始まわり=八代市。家庭でおとそや雑煮で新年を祝い、上司や親類の家に年始

公役の昼食=八代市。球磨川河口堤下は葭やすき、茅などが繁茂し舟着き場にも影響するので定期的に公役が行われた。帳付さん(世話係)は昼飯時に人数を確認する。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年11月05日
撮影:1952年11月
公役の昼食=八代市。球磨川河口堤下は葭やすき、茅などが繁茂し舟着き場にも

かやぶき屋根=八代市。茅葺きは親類や近隣の男衆が総出で手伝った。夏は涼しく冬は暖かく、先祖から受け継いだ家を代々大切に守った (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年10月17日
撮影:1952年10月
かやぶき屋根=八代市。茅葺きは親類や近隣の男衆が総出で手伝った。夏は涼し

馬車=八代市。八代市金剛付近ではのどかな馬車が、村の人たちの足でもあった。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年08月12日
撮影:1952年8月
馬車=八代市。八代市金剛付近ではのどかな馬車が、村の人たちの足でもあった

川を渡って野良帰り=八代市。八の字堰が出来る以前、下流での農作業後、植柳橋の方に戻るには小さな川岸の道を通った。降雨で道が水浸しになっても、水の流れる道を黙々と歩いて家へ帰る (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年07月05日
撮影:1952年7月
川を渡って野良帰り=八代市。八の字堰が出来る以前、下流での農作業後、植柳

川を渡る野良帰り=八代市。球磨川河口一帯の田畑で農作業をして家に帰る時、雨は振らなくとも上流で降雨があると川のそばの道は水びたしになった。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年07月05日
撮影:1952年7月
川を渡る野良帰り=八代市。球磨川河口一帯の田畑で農作業をして家に帰る時、

藻切り舟=八代市。流藻川という名前通り、川底に藻が繁茂。田植え前には、舟尾に取り付けた発動機に回転羽を付け、藻を切り取り掃除した (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年05月20日
撮影:1952年5月
藻切り舟=八代市。流藻川という名前通り、川底に藻が繁茂

藻切り舟=八代市催合町。八代市高田から日奈久町までの流藻川は、「藻」がぎっしり生え、ゴミ箱がひっかかったりする。四季を通じ、舟で発掃除した (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和27年05月10日
撮影:1952年5月
藻切り舟=八代市催合町。八代市高田から日奈久町までの流藻川は、「藻」がぎ
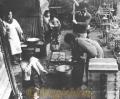
餅つき=八代市。「もち米」洗い「蒸籠」と云う木製の四角いわくの底に細い竹ヒゴを糸で編んだ「ミス」を敷く。もち米を入れ、釜の上で湯気で蒸す。石や木の臼に入れ、杵でついていく。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和26年12月28日
撮影:1951年12月
餅つき=八代市。「もち米」洗い「蒸籠」と云う木製の四角いわくの底に細い竹
