
トップページ > カテゴリー「八代」 での検索結果(1722件ヒット)


まもなくスタートします・・・

金剛干拓の住宅建設。地区内の道路もいまだ整備されておらず、用排水も未完成で一雨降れば一面水浸しだった=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和31年01月01日
撮影:1956年1月
金剛干拓の住宅建設=八代市

金剛干拓の住宅建設。大工・左官・鉄工など各工程が忙しく農作業のヒマはない。田んぼでの作業や洗濯などは同時に進んでいた=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和31年01月01日
撮影:1956年1月
金剛干拓の住宅建設=八代市

金剛干拓の住宅建設。宅地はいつも水がたまっていたのでゴムタイヤにロープをつけ運んだりした。「飲み水」は良質な水が湧いていたのが幸いだった=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和31年01月01日
撮影:1956年1月
金剛干拓の住宅建設=八代市

道しるべ=八代市。現在、旭中央通りや、ハーモニーホールの南西部にあるこの石碑の前も川だった。川が道路に変わっても、石の道しるべは一部損傷しながらも残っている (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年12月05日
撮影:1955年12月
道しるべ=八代市
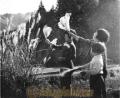
ススキ遊び=八代市。ススキの穂を振り口ずさむ。「しゃぼん玉飛んだ…風にのって消えた。」野口雨情が見たらどんな童謡にしただろう。元気で明るい20世紀の女の子。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年11月15日
撮影:1955年11月
ススキ遊び=八代市。ススキの穂を振り口ずさむ。「しゃぼん玉飛んだ…風にの

サーカスの象=八代市。八代宮境内でサーカスの興業があり、貨物専用の球磨川駅に象が到着。PRで八代宮まで行進する前に、子どもたちに長い鼻をふりあいさつした (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年10月18日
撮影:1955年10月
サーカスの象=八代市。八代宮境内でサーカスの興業があり、貨物専用の球磨川

焼き芋もメートル法で=八代市。尺貫法がメートル法に改正され、焼き芋100匁15円が375g15円になり、人々も慣れるまでは月日がかかった (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年10月02日
撮影:1955年10月
焼き芋もメートル法で=八代市。尺貫法がメートル法に改正され、焼き芋100

油谷工業製作の「ユンボ」が掘削作業に役だった=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年10月01日
撮影:1955年10月
油谷工業製作の「ユンボ」が掘削作業に役だった=八代市の金剛干拓

金剛干拓の排水路工事。掘削用の重機では作業ができず人力で行ったので工事がなかなか進まなかった=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年10月01日
撮影:1955年10月
金剛干拓の排水路工事=八代市

大江湖網開き。9月中旬の農閑期になると、海と背中合わせの大江湖では「網びらき」が行われる=鏡町 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年09月17日
撮影:1955年9月
大江湖網開き=鏡町

タブ攻め=鏡町。大江湖は干拓地の遊水池で樋門の外は八代海。土地の言葉で遊水地を「ダブ」と呼び、年一回「ダブ攻め」という網開きが行われ、大きなボラや鯉、フナなどが捕れる。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年09月08日
撮影:1955年9月
タブ攻め=鏡町。大江湖は干拓地の遊水池で樋門の外は八代海

浚渫機=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年09月08日
撮影:1955年9月
浚渫機=八代市

干潟の漁=八代市。潮が引いた干潟の穴にいる「貝」や「しゃく」をとるため、大島付近で潮が満ちてくるまで、どろんこになって漁をした。現在は干拓され工業団地になっている (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年09月05日
撮影:1955年9月
干潟の漁=八代市。潮が引いた干潟の穴にいる「貝」や「しゃく」をとる

用・排水路、樋門工事など井戸工事、廃水まで発動機が活躍したので点検、修理も忙しかった=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年09月03日
撮影:1955年9月
発動機の点検、修理=八代市の金剛干拓

客馬車=八代市。「パッカパッカ」ひずめの音が軽快なリズムをとり、ゆったりと走る「客馬車」に子どもたちは大喜び。盆、正月やお祭りには子どもたちでいっぱいだった (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年08月15日
撮影:1955年8月
客馬車=八代市。「パッカパッカ」ひずめの音が軽快なリズムをとり、ゆったり
