
トップページ > カテゴリー「八代」 での検索結果(1722件ヒット)


まもなくスタートします・・・

妙見祭神幸行列の人気者、「亀蛇」。早朝の出発前、見送る町内の人たちに首を上げてあいさつする=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年11月18日
撮影:1960年11月
妙見祭の亀蛇=八代市。妙見祭神幸行列の人気者、「亀蛇」

七五三参り=八代市。子どもの成長を祝う行事。「羽織袴」を背丈の伸びに従い、「紐解き」という縫い代を上げ(伸ばし)て神社に参拝。親類や町内にも見せ、子どもの成長を祝った。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年11月15日
撮影:1960年11月
七五三参り=八代市。子どもの成長を祝う行事。「羽織袴」を背丈の伸びに従い

休日に洗い物の手伝いをする子どもたち=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月30日
撮影:1960年10月
休日に洗い物の手伝いをする子どもたち=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影)

農繁期が過ぎ、運動やレクレーションを楽しむ入植者=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月30日
撮影:1960年10月
農繁期が過ぎ、運動やレクレーションを楽しむ入植者=八代市の金剛干拓

お遊戯=八代市。ばらが咲いた…きれいだなーと父兄の前で踊る。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月18日
撮影:1960年10月
お遊戯=八代市。ばらが咲いた…きれいだなーと父兄の前で踊る。 (麦島勝氏

刈り穂の干し場がない農家は、牛・馬にひかせて干し場まで運搬していた=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月12日
撮影:1960年10月
刈穂運び=八代市

交通整理の児童=八代市。霧でかすんだ朝は二人で連携して素早く指示誘導する。大人たちも喜んで協力した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月11日
撮影:1960年10月
交通整理の児童=八代市。霧でかすんだ朝は二人で連携して素早く指示誘導する

夜行列車=肥薩線坂本駅付近。3等車の通路には新聞紙が敷かれ座ったり寝ころんだり、立ちうどんの容器が捨てられており車掌さんが掃除して廻った。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年10月09日
撮影:1960年10月
夜行列車=肥薩線坂本駅付近。3等車の通路には新聞紙が敷かれ座ったり寝ころ

舟作り=八代市。船首から船尾までのカーブに合わせて「手斧(チョウナ)で削られた「竜骨」が組み立てられる。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年09月18日
撮影:1960年9月
舟作り=八代市。船首から船尾までのカーブに合わせて「手斧(チョウナ)で削
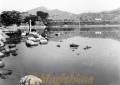
旧萩原橋=八代市。急峻な球磨川の遥拝堰下流は、川幅が広くなり流れもゆるやかになる。右岸には豊国旅館が残っている (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年05月15日
撮影:1960年5月
旧萩原橋=八代市。急峻な球磨川の遥拝堰下流は、川幅が広くなり流れもゆるや

日本セメント工場の右側は三楽オーシャン工場があり国鉄八代駅から両工場まで引き込み線でSLが往復していた=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年05月11日
撮影:1960年5月
日本セメント=八代市。日本セメント工場の右側は三楽オーシャン工場

築堤工事=八代市。八代内港の工事で天草から運ばれた石を天びん棒で担ぎ、凸凹した現場を何回も運搬した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年02月01日
撮影:1960年2月
築堤工事=八代市。八代内港の工事で天草から運ばれた石を天びん棒で担ぎ、凸

寒行=八代市。大寒に入り、上人さんを先頭に信者たちが「南無妙法蓮華経」と唱えながら、団扇太鼓を打ち鳴らし、村や町を歩く。寒さに耐え日蓮宗の寒行 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年01月20日
撮影:1960年1月
寒行=八代市。大寒に入り、上人さんを先頭に信者たちが「南無妙法蓮華経」と

球磨川一週駅伝=坂本村。八代宮前から国道219号沿いの球磨川流域を人吉市まで走る駅伝競走が行われた。折からの雪にも負けず選手も観衆も一生懸命に走り、声援を送った (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年01月15日
撮影:1960年1月
球磨川一週駅伝=坂本村。八代宮前から国道219号を人吉市へ

雪の駅伝=球磨村。「球磨川一周駅伝」。沿岸道路とも呼ばれた県道304号の完成を祝い、八代宮前から国道219号線沿いの球磨川流域を人吉まで走った。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年01月15日
撮影:1960年1月
雪の駅伝=球磨村。「球磨川一周駅伝」。沿岸道路とも呼ばれた県道304号の
