
トップページ > カテゴリー「阿蘇地方」 での検索結果(2868件ヒット)


まもなくスタートします・・・

牛の背に揺られて=高森町。舗装もない山道はでこぼこしていた。町へ出掛けるときは家族で。先頭は父か兄で数頭の牛や馬の鞍に綱をつなぎ幼い子どもも上手に鞍にまたがり乗りこなしていた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和25年11月01日
撮影:1950年11月
牛の背に揺られて=高森町。舗装もない山道はでこぼこしていた。町へ出掛ける

牛ならし=高森町。朝起き、顔洗い、「牛ならし」と小学校に行くまでの少年たちは親からしつけられた。少年がならされている畜産農家ならではの日常風景である (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和25年07月05日
撮影:1950年7月
牛ならし=高森町

豊作祈願の火渡り=阿蘇町。この田に幸あれとしばしご婦人連によるゴエイ歌が奏せられる (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和25年04月15日
撮影:1950年4月
豊作祈願の火渡り=阿蘇町。この田に幸あれとしばしご婦人連によるゴエイ歌が

豊作祈願の火渡り=阿蘇町。ゴマ木が燃え上がり、(これはけがれを清める意味)集落の人たちは静かに見守る (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和25年04月15日
撮影:1950年4月
豊作祈願の火渡り=阿蘇町。ゴマ木が燃え上がり、(これはけがれを清める意味

冬の牧草運び=小国町。草泊まりで作った干草は、山の牧草貯蔵小屋に保管。時々馬の背に乗せて家まで運ばれた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和25年02月05日
撮影:1950年2月
冬の牧草運び=小国町。草泊まりで作った干草は、山の牧草貯蔵小屋に保管。時

代かきの共同作業=長陽村。せまい段々畠が多い山間地では、早朝から地区の農家が共同の田植え。あぜがくずれた田んぼは牛馬の背に積んだ「わら」で水止めの応急処理を行う。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和24年05月22日
撮影:1949年5月
代かきの共同作業=長陽村。せまい段々畠が多い山間地では、早朝から地区の農

棚田=阿蘇郡長陽村立野。棚田が連なり壮観な眺めだ。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和23年11月20日
撮影:1948年11月
棚田=阿蘇郡長陽村立野。棚田が連なり壮観な眺めだ。 (麦島勝氏撮影)

草泊まり=小国町。冬の牛馬の飼料になる干し草をつくるため、阿蘇の高原に寝泊まりして草刈りをした。子どもたちも学校を休み、かやぶきの家で手伝い、夜は仲良く勉強した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和22年11月11日
撮影:1947年11月
草泊まり=小国町。冬の牛馬の飼料になる干し草をつくるため、阿蘇の高原に寝

草泊まり=小国町。高原に寝泊りし、草を刈り、冬の牛馬のための干草作り。夜まで子供たちも手伝う。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和22年11月11日
撮影:1947年11月
草泊まり=小国町。高原に寝泊りし、草を刈り、冬の牛馬のための干草作り。夜

国鉄立野駅付近。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
国鉄立野駅付近。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)

牛の背。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
牛の背。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)

田植え其一。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
田植え其一。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)
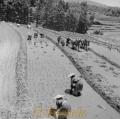
田植え其三。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
田植え其三。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)

田植え其九。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
田植え其九。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)

田植え其二。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影) 撮影日:昭和13年06月22日
撮影:1938年6月
田植え其二。瀬田村立野 (楠田宗光氏撮影)
