
トップページ > カテゴリー「阿蘇地方」 での検索結果(2868件ヒット)


まもなくスタートします・・・

草千里冬の朝・ミヤマキリシマに付着した霧氷=阿蘇市。朝日が当たる時、サンゴのような輝きを見せる。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成6年02月11日
撮影:1994年2月
草千里冬の朝・ミヤマキリシマに付着した霧氷=阿蘇市。朝日が当たる時、サン

阿蘇谷雲海・2=阿蘇・北外輪。晩秋の阿蘇谷を覆う雲海。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成5年11月01日
撮影:1993年11月
阿蘇谷雲海・2=阿蘇・北外輪。晩秋の阿蘇谷を覆う雲海。 (福嶋俊郎氏撮影

阿蘇谷雲海。11月にしては見事な雲海が発生した。朝日に照らされた雲海が赤く染まる。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成4年11月01日
撮影:1992年11月
阿蘇谷雲海。11月にしては見事な雲海が発生した。

阿蘇谷雲海・5=11月にしては見事な雲海が発生した。朝日に照らされた雲海が赤く染まる。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成4年11月01日
撮影:1992年11月
阿蘇谷雲海・5=11月にしては見事な雲海が発生した。朝日に照らされた雲海

高原の風=阿蘇山・北外輪。高原の秋風に朝日を浴びたススキが黄金の穂を揺らす。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成4年10月25日
撮影:1992年10月
高原の風=阿蘇山・北外輪。高原の秋風に朝日を浴びたススキが黄金の穂を揺ら

朝霧=阿蘇・大観峰。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:平成2年11月01日
撮影:1990年11月
朝霧=阿蘇・大観峰。 (福嶋俊郎氏撮影)

阿蘇谷雲海・1=阿蘇市の二重の峠より。二重の峠から阿蘇谷を東方向に望む来、阿蘇五岳と祖母山を画面に入れる事が出来る。 (福嶋俊郎氏撮影) 撮影日:昭和63年10月01日
撮影:1988年10月
阿蘇谷雲海・1=阿蘇市の二重の峠より。二重の峠から阿蘇谷を東方向に望む来

飯食い祭り=高森町。各集落の接待客は、大盛りのご飯を腹いっぱいおかわりして食べる。そして代表選手となるので子供たちの声援で大賑わい。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和59年12月10日
撮影:1984年12月
飯食い祭り=高森町。各集落の接待客は、大盛りのご飯を腹いっぱいおかわりし

飯食い祭り=高森町。祭りのために、高さ30cm直径15cmの「大塔飯」が作られる。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和59年12月10日
撮影:1984年12月
飯食い祭り=高森町。祭りのために、高さ30cm直径15cmの「大塔飯」が

飯食い祭り=高森町。色見地区には4つの集落がある。この日は、山鳥が接待役で昼から男ばかりで料理した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和59年12月10日
撮影:1984年12月
飯食い祭り=高森町。色見地区には4つの集落がある。この日は、山鳥が接待役

飯食い祭り=高森町。350年の歴史をもつ伝統行事。秋の収穫が終わり、新米を持ち寄って貴重な白米をたらふく食べ、翌年の豊作を願ったのが起源と云う。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和59年12月10日
撮影:1984年12月
飯食い祭り=高森町。350年の歴史をもつ伝統行事。秋の収穫が終わり、新米

田楽料理=高森町。田楽はいろりを囲み家族で食べる阿蘇の郷土料理。レジャーで訪れた知人などから口コミで広がって、高森の人気料理になった。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和55年10月02日
撮影:1980年10月
田楽料理=高森町。田楽はいろりを囲み家族で食べる阿蘇の郷土料理。レジャー
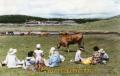
ピクニック=阿蘇草千里。赤牛が放牧された、草原で家族連れがお弁当を広げていた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和54年09月02日
撮影:1979年9月
ピクニック=阿蘇草千里。赤牛が放牧された、草原で家族連れがお弁当を広げて

野良帰り=高森町。牛に刈り草などを運ばせ、家に帰る (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和54年09月02日
撮影:1979年9月
野良帰り=高森町。牛に刈り草などを運ばせ、家に帰る (麦島勝氏撮影)

ひと休み=高森町。根子岳の東南の麓、鍋の平高原一帯は秋が深まると冬期の飼料となる牧草を切りをする。子供たちも父母のそばで手伝ったり遊んだりする。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和50年11月18日
撮影:1975年11月
ひと休み=高森町。根子岳の東南の麓、鍋の平高原一帯は秋が深まると冬期の飼
